📌 息が詰まる“二択の壁”、あなたも経験ありませんか?
「『はいかいいえで答えて』って言われて、息苦しくなった経験、ありませんか?」
なんとなく笑ってごまかしてしまったあの日の自分を思い出す。でも、心の中で「どうしてこんな聞き方をするんだろう?」とモヤモヤしてませんでしたか?
私自身、何度もそうでした。
素直に答えたはずなのに、話がどんどん自分の知らない方向へ進んでいく――そんな独特の悔しさを覚えたことがあるんです。
今回はそんなモヤモヤを、誰かと一緒に“解剖”してみようと思います。「二択で答えさせる会話術」の本質に迫る話、いってみましょう。
🧩 1. 「はい/いいえ」だけに押し込むズルさとは?
-
選択肢を限定=主導権を握る:二択を強制することで、聞き手が有利な方向に話を誘導できます。
-
真意が伝わらない:言葉の裏側にある“葛藤”や“条件付きでのNO”などを拾いようがありません。
-
相手の善意を逆手に取る:空気を読んで答えてしまう人ほど、都合よく話が進む構造です。
この聞き方は、知らない間に相手の“思考を止める”力を持っています。「ほんとはそう思ってないけど…」っていう声が埋もれてしまうんです。
🧠 2. 意図的な論点のすり替え──ストローマン論法ってやつ
ストローマン論法(藁人形論法)は、相手の主張を意図的に“ねじ曲げ”“あえて弱く”して、それを批判する手口。
-
例:「〇〇社の会議は長すぎ→つまり会議不要って言いたいの?」
本来は「効率化したいだけ」のところを「無駄だと言ってる」と変えられてしまう。
最近のネットやSNSでも、わざと誤解を生む言い回しで論点をすり替える投稿が多く見られます。
📌 短文・煽りコメントがバズる構造では、こうした手法が非常に効くんです。
👥 3. 空気を読む人の“善意”は摩耗しやすい
「はい」と答える人ほど、
-
相手の機嫌を気にして、
-
波風を立てたくなくて、
-
変に思われたくなくて…。
その“優しさ”が逆手に使われやすく、
あとから「あなたがYESだったから進めた」なんて言われて、
言葉が武器のように扱われるって、冷静に考えたらけっこう怖い話です。
📊 よくある影響と構造を図解すると…
二択を強制 → 余白がなくなる → 会話の主導権は聞き手へ
↓
発言者は “思考停止”・“誤解”・“後出し批判” を招く
🧭 4. 抑圧ではなく、対話の“余白”を取り戻すために
✔️ ストローマン論法への対処法
-
「あなたの言いたいのって、〇〇ですか?」 と確認する
-
「それって本当は△△って感じません?」 と言葉の背景に踏み込む
✔️ 二択を避ける対話の設計
-
「どんな場合だったら?」を添えた質問に変える
-
「YESでもNOでもなく、□□的にはどう?」と問い直す
🧩 5. 引用:SNSでの“あるある”反応
読者から寄せられたリアルな声(匿名):
「『はい』だけ言ったら、後で都合よく切り取られてて、ゾッとしました…」
「黙って合わせちゃうタイプだから、こんな風に使われてるとは思わなかった」
こういう声が示すのは、表面的な“従順さ”が本当は反発の火種になっていること。
読者にも「これ、自分のこと?」と刺さる実例になるはずです。
✅ 6. まとめ:言葉の余白を奪う会話には未来がない
「はい/いいえ」に押し込められた会話は、心の声を潰す道具になり得ます。
でも、それを指摘するのは“わがまま”じゃなくて、“人としての主張”。
対話とは互いの思いをすくい合いながら進む道。
だからこそ、二択の罠には気づき、明るく柔軟な“余白ある聞き方”を選びたいですね。
|
|
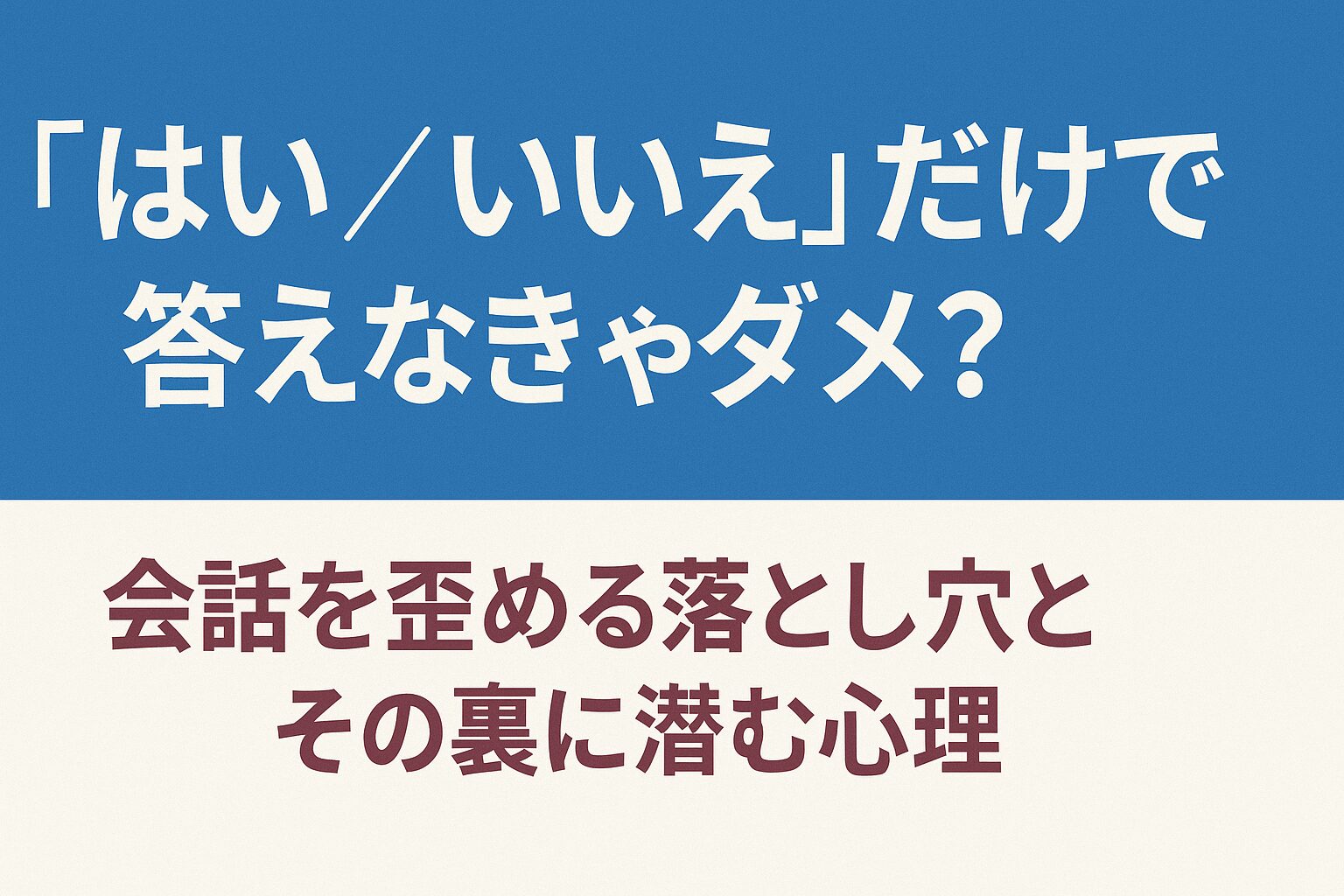




コメント