どうも、こんにちは-はじめまして。
Webライターの「あき」といいます。よろよろです。
突然ですが、みなさん、普段何気なく使っている言葉や、当たり前のようにしている習慣について、「これって、なんでこうなったんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
私はしょっちゅうです。
例えば、おやつの時間は「3時」が定番だけど、なんで3時なんだろう?とか、
海外の人と会う時に「握手」をするのは、一体いつから始まったんだろう?とか。
私自身、この仕事をしていると、色々な情報に触れる中で「え、これも!?」と驚くような事実に出くわすことがあります。
そして、その背景を知るたびに、「私たちの日常って、想像以上に奥深いんだな」と、なんだか感動してしまうこともしばしば。
今日の記事では、そんな「なぜ?」が「なるほど!」に変わる、
日常に潜む言葉や習慣の“超”意外なルーツを10個ご紹介します。
もしかしたら、この記事を読み終わった後、あなたの何気ない毎日が、ちょっぴり違って見えるかもしれません!😉✨(かもです、かも)
💡 知ればもっと面白くなる!言葉と習慣の驚くべき起源
つーわけで特に気になったものを10個ほど紹介していきます。
1. なぜ「おやつ」は「3時」なの?🕰️
「3時のおやつ」は、もはや日本の国民的習慣と言っても過言ではありませんよね。でも、これっていつから、なぜ「3時」なんでしょう?
実はこれ、江戸時代の時刻制度が関係しています。当時、時刻は「九つ時」「八つ時」のように数えられていました。「八つ時」は現在の午後2時から4時頃を指し、この時間帯に軽食をとる習慣があったんです。そこから「八つ時」に食べるもの、略して「おやつ」と呼ぶようになり、やがて西洋式の時計が普及する中で、だいたい「午後3時」に定着していったと言われています。
つまり、「おやつ」は江戸時代からの由緒正しい休憩習慣だったんですね!
⇒3時より「おやつ」の由来の方が「はぇー、ほーん」ってなった笑
ちなみに職人さんのバイトしていたときの話なんですが、そのときは10時のおやつもあった。朝早かったからかもしれんが。
2. 「パン」と「ごはん」の呼び名の由来は?🍞🍚
私たちの主食である「パン」と「ごはん」。それぞれの呼び方には、意外な歴史が隠されています。
「パン」は、16世紀にポルトガルから日本に伝えられた際に、ポルトガル語の「pão(パォン)」がそのまま使われるようになったもの。
一方、「ごはん」は、漢字の「御飯」から来ていますが、元々は炊いた米だけでなく「食事」そのものを指す言葉でもありました。神様にお供えする「御饌(みけ)」が転じて「飯(いい)」となり、そこに丁寧語の「御(お)」が付いて「御飯」になった、という説が有力です。
外来語と日本語、それぞれのルーツを知ると、食文化の多様性が見えてきますね。
⇒パンは英語で?「パァン!!」とか言ってるおバカさんもいたような・・・
3. 「乾杯」の習慣はどこから来た?🥂
お祝いの席などで、グラスをカチンと合わせる「乾杯」。
一体なぜ、こんな習慣が生まれたのでしょう?
有力な説はいくつかあります。
-
悪魔払い説:昔、お酒に毒が盛られることを恐れ、グラスを勢いよくぶつけ合って、お酒を混ぜることで毒を無効化しようとした、という説。また、グラスがぶつかる音で悪魔を追い払うという意味もあったとか。
-
連帯感の象徴:同じお酒を分かち合うことで、仲間意識や連帯感を高める意味合いがあった、とも言われています。
いずれにしても、単なる儀式ではなく、人々の「安全」や「結束」への願いが込められた行為だったんですね。
⇒悪魔とかいうあたり、海外由来な気もしますね。日本だけだったらグラスを当てる文化はなかったんですかね。もうちょい調べてみたい。
4. 「握手」はなぜするようになった?🤝
初対面の人や旧知の友人と交わす「握手」。
ごく自然な行為ですが、これも深い意味を持っています。
そのルーツは、古代に遡ります。相手に武器を持っていないこと、敵意がないことを示すために、お互いの右手を差し出し、握り合う習慣が生まれたと言われています。
中世ヨーロッパでは、契約や同盟を結ぶ際に、お互いの信頼と合意を示す儀式としても行われました。現代では、挨拶や和解、お祝いなど、世界中で友好や敬意を示す普遍的な行為となっています。シンプルな動作に、こんなにも深い歴史が詰まっているなんて驚きです。
⇒これが今や握手で煽ったり、手に画鋲をしこんだり・・・おじさん悲しいぜ。
5. なぜ「お辞儀」をするの?🙇♀️
日本独自の文化と思われがちですが、「お辞儀」にも奥深い歴史と意味があります。
お辞儀のルーツは諸説ありますが、古くから相手への敬意や服従、あるいは感謝の気持ちを表す行為として行われてきました。頭を下げることで、自分の無防備な部分を見せ、相手に敵意がないことを示し、信頼関係を築くための重要なコミュニケーション手段だったのです。
時代とともにその形は変化しましたが、今もなお、日本人の礼儀作法として大切に受け継がれていますね。
⇒だから土下座とかも多分そうですよね。だからこそだまし討ちなんかしちゃいけない。
6. 「いただきます」「ごちそうさま」の本当の意味は?🙏
食事の前に「いただきます」、食後に「ごちそうさま」。普段使いすぎて、その意味を深く考えることは少ないかもしれません。
-
「いただきます」:元々は「命をいただく」という意味が込められています。食材となった動物や植物の命、そしてその命を育んだ自然、調理してくれた人への感謝を表す言葉です。
-
「ごちそうさま」:「ご馳走様」の「馳走」とは、元々「走り回る」という意味。お客さんをもてなすために、食材を求めて走り回ったり、準備に奔走したりする様子を表していました。つまり、「ごちそうさま」は、食事のために奔走してくれた人への感謝の気持ちを伝える言葉なんです。
食べ物への感謝、そして関わるすべての人への感謝。日本の食文化の奥深さを感じさせられます。
⇒これは日本ならではですよね。すごく素敵なことだと思います。
「ありがとう大地 ありがとう太陽 命をありがとう いただきます」
7. なぜ「指切りげんまん」をするの?👆
子供の頃、約束をする時に「指切りげんまん、嘘ついたら針千本飲ます、指切った!」なんて歌いませんでしたか?
この「指切り」のルーツは、江戸時代の遊女が客への愛情を示すため、あるいは誓いを立てるために自分の指を切って渡した、という恐ろしい習慣に由来すると言われています。また、誓約を破った場合の罰則として、指を詰める(切る)という習慣もありました。
それが時を経て、子供たちの間で「約束を破ったら大変なことになる」という戒めを込めた遊びへと変化していったんですね。意外な過去にゾッとしますが、それだけ約束の重みを伝える習慣だったのでしょう。
⇒”げんまん”が”拳骨万回”ってどっかの漫画にあったような気がするんだが忘れてしまった。。
あと針千本て”千本の針”じゃなくて”ハリセンボン”だって聞いたんだけど、
そもそも「ハリセンボンって何??」って思った子供時代でした。
8. 「ジャンケンポン」の掛け声の由来は?✊✌️🖐️
グー、チョキ、パーで勝敗を決める「ジャンケン」。その独特な掛け声にもルーツがあります。
「ジャンケン」の原型は、中国から伝わった「虫拳(むしけん)」や「狐拳(きつねけん)」といった「拳遊び」にあるとされています。これらは、親指がヘビ、人差し指がカエル、小指がナメクジといったように、動物に見立てた指を使って勝敗を決めました。
「ジャンケンポン」という掛け声は、これらの拳遊びの掛け声が時代とともに変化し、語呂が良い形に定着したものと考えられています。江戸時代後期には「石拳(いしけん)」という、現在のジャンケンに近い遊びが広まっていたようです。
遊びの掛け声にも、こんな歴史が詰まっているなんて面白いですよね。
⇒ハンターハンターを思い出す。ジャジャンケン。。
block, paper, scissorsってのもやっぱ原作リスペクトなんすね。
9. なぜ「くしゃみ」が出たら「誰かが噂している」と言うの?🤧🗣️
「誰かが噂してるんじゃない?」なんて言われる「くしゃみ」。これにも古くからの迷信が関わっています。
世界各地に似たような言い伝えがありますが、日本では昔から、くしゃみは魂が体から抜け出そうとしている状態だと考えられていました。そのため、くしゃみが出たときに、誰かが自分の噂をしていると考えることで、魂が抜け出すのを防いだり、周囲の人にその存在を知らせたりする意味合いがあったと言われています。
また、くしゃみが病気の兆候であることから、それを避けるためのまじない的な意味合いもあったようです。科学的根拠はなくても、人々の素朴な信仰心が表れていますね。
⇒「くしゃみがでた!抜けるな魂よ!!」じゃなくて「っくしゅん!誰かが噂してるな」ってちょっと意味がわからんのだが笑
10. 「厄年」って本当に厄介なの?その由来は?🔥
人生の節目に訪れるとされる「厄年」。なんとなく不吉なイメージがありますが、そのルーツは何でしょうか?
厄年の概念は、古代中国の陰陽道(おんみょうどう)や、日本の民間信仰に深く根ざしています。特定の年齢は、肉体的・精神的な変化が大きく、災厄に見舞われやすい時期である、という考え方から生まれました。
厄年には、体調を崩しやすかったり、人生の転機を迎えたりすることが多いため、「慎重に過ごしなさい」という先人たちの知恵や戒めが込められているとも言えます。厄払いをすることで、心の平穏を得るという側面も大きいですね。
⇒これすごい思ったんですよ、ちょうどなんかある感じの年齢のところが厄年近いの。
たぶん昔からのデータの積み重ねで決まって行ったんだろうなと思いつつ、
時代の流れに合わせて調整していくべきなのではないのかなと思ったりするんです。
神社にもよるけど、厄年は
男性・・・25歳、42歳、61歳
女性・・・19歳、33歳、37歳、61歳
になってて、これ絶対結婚とか妊娠とか冠婚葬祭とかと関係してると思うんですよね。
で、晩婚化とか長寿化とか踏まえたら再調整したほうがいいのかなと思ったり。
※あくまで推測です。
この考察だけで1記事書けそう。
💬 この雑学、みんなはどう思いました?反応を予想
以下のようなことを思ったんじゃないかと思うんですが、違ってたらコメントで教えてください。
-
「え、おやつって江戸時代から!?知らなかった!」
-
「『いただきます』の本当の意味を知って、食べる時の気持ちが変わった…」
-
「ジャンケンの由来、まさかそんなに古くからあるとは!面白い!」
-
「握手のルーツ、昔は命がけだったんだな…と考えると感慨深い」
-
「厄年の考え方、単なる迷信じゃなくて、先人の知恵って言われると納得する」
特に、普段何気なく使っている言葉やしている行動の裏に、深い歴史や意味が隠されていることに驚きや感動を覚えますよね。
新しい発見を通じて、日々の生活がより豊かに感じられる、というのが本記事の目的です(後付け)
🌈 まとめ:日常は「なぜ?」の宝庫!
というわけでそろそろ終わります。
今回ご紹介した10の雑学は、ほんの一部に過ぎません。私たちの周りには、「なぜ?」と思わず口にしてしまうような、面白い言葉や習慣がまだまだたくさん眠っています。
これらのルーツを知ることは、単なる知識の蓄積にとどまらず、文化や歴史、そして人々の暮らしへの理解を深めることにつながります。そして何より、日常がちょっぴり面白くなるきっかけになるはずです。
もしこの記事を読んで、何か一つでも「へぇ!」と心に残る発見があったなら、とても嬉しいです。
ぜひ、今日からあなたの身の回りにある「なぜ?」を探してみてください。きっと、新しい「なるほど!」があなたを待っていますよ!😉✨
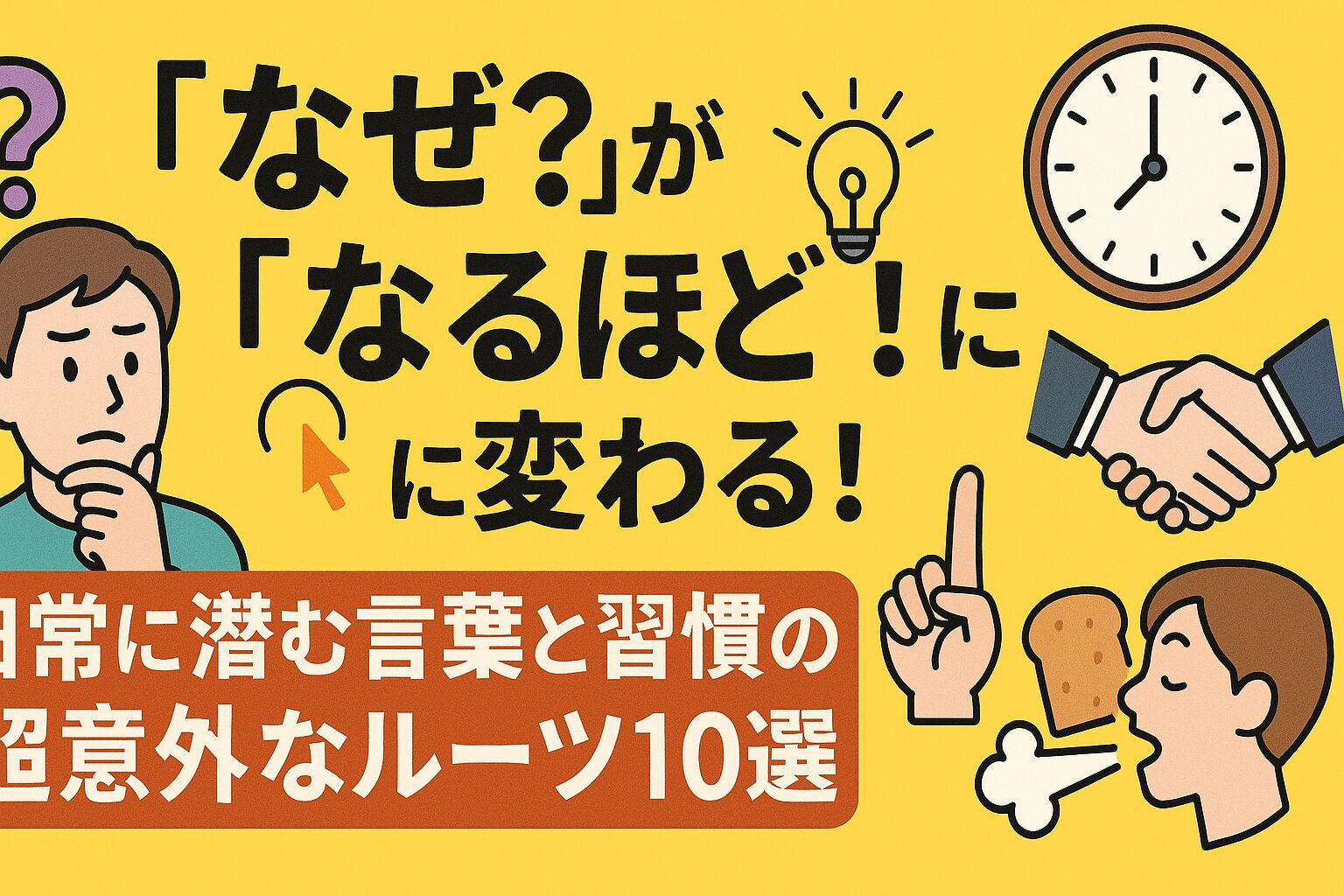
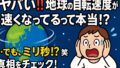
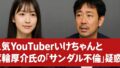
コメント