1. はじめに
大学時代、某中華チェーンでバイトを始めた私。
その私に対して友人から信じられない質問がきた。
「〇〇ってスープ使いまわしなんでしょ?」
・・・・?
なんだ、こいつは。一体何を言っているんだ?
で、最近思ったんです。そう考えている人は他にもいるんじゃないか。
何か根拠があって言っているのではないか?
で、調べてみてある程度いろいろわかってきたのでまとめました!
SNSや居酒屋で囁かれる“ラーメン屋の飲み残しスープ再利用説”は、ネットの普及以降、まるで都市伝説のようにひとり歩きしています。
しかし、本当にそんなことが起こり得るのでしょうか?食品衛生の専門家はどう評価するのか?今回は、その“デマ”を法律と現場の視点から検証し、安心してラーメンを味わうためのポイントもあわせてご紹介します。
読者の皆さんも、一度は「本当かな?」と疑った経験があるはず。
単なる否定にとどまらず、実際の法文や業界常識、地域にまつわる噂話の検証を交えながら、“安心してラーメンを楽しむコツ”をお届けします。
デマに振り回されないために、一緒に確認していきましょう。
2. 噂の内容を整理
まずは、流布している噂の全容を整理します。
-
スープ残りを翌日も再利用
「一度提供したお客さんの飲み残しを鍋に戻して温め直し、別のお客さんに出しているのでは?」 -
付け合わせのパセリを洗って何度も使い回す
「フライドポテトに載っているパセリが妙にしおれているのは、前日の残りだからでは?」
⇒「パセリ食べないの?」って聞いたら「やだよ!使いまわしじゃん!」って言われたことがあるんすよ!!私。
これらの話は、飲み会や掲示板で断片的に語られ、裏取りされないまま「ラーメン屋では当たり前」と誤解されてしまうケースが少なくありません。
アホかと思いますがね。
しかし!でもでも!果たしてアホはどっちなのか・・・。
3. 事実確認:法律と業界常識
3.1 食品衛生法の視点
食品衛生法では、一度提供した「食べ残し」を再利用する行為を明確に禁止しています。
-
食品衛生法第52条:「飲食店が既に提供した食品を再度販売してはならない」
-
違反した場合は、営業停止命令や罰金、最悪の場合は懲役刑が科される可能性があります
この規定がある限り、たとえ業務が多忙でも“洗って再利用”は絶対に行われません。
店側にとっても、リスクだけが大きくメリットは皆無です。
3.2 プロの現場でのスープ管理
実際のラーメン店では、安全性と美味しさを両立させるため、以下の方法でスープ管理を行っています。
-
まとめ炊き&小分け保存
-
朝の仕込みで大量にスープを炊き、適温まで冷却。
-
タンクやステンレスタンクに小分けにして保存し、提供時に再加熱。
※小分けにせず大きな鍋で炊き続けるラーメン屋さんもたくさんあります
-
-
香味油・タレの継ぎ足し
-
ネギ油や鶏油などの香味油、醤油ダレは風味を保つ要。提供量に応じて継ぎ足し、味を安定させる。
-
-
在庫管理の徹底
-
当日分のスープは当日中に使い切るのが基本。翌日に持ち越さない運用で、衛生リスクを防いでいる。
-
この流れを見れば、“飲み残し再利用”どころか、衛生面・品質面でのメリットが一切ないことがお分かりいただけるでしょう。
4. デマが生まれる原因
噂話が独り歩きする背景には、主に以下の3つの要因があります。
4.1 見た目・匂いの些細な違和感
-
毎日の仕込み量や火加減、使用する具材が微妙に異なるため、同じ店舗でもスープの色味や香りが変化しやすい。
-
お客さんが「昨日と違う」「油膜が多い」と感じることで、使い回し疑惑が生まれやすくなります。
4.2 “業務効率化”イメージの誤解
-
ラーメン屋は長時間にわたって調理や接客を行うため、「コスト削減のために同じスープを使い続けるのでは?」と短絡的に想像されがちです。
4.3 SNS/口コミでの裏取り不足な情報拡散
-
「友達が見た」「先週話題になっていた」といった不確かな一次情報が、Twitterや匿名掲示板で拡散。
-
真偽を問わずシェアしやすいため、デマが一気に広がってしまいます。
5. 実際に語られる“使い回し”エピソード検証
以下の表は、全国で囁かれるラーメン屋“スープ&パセリ使い回し”の代表的な噂をピックアップし、保健所記録や報道、口コミサイト情報をもとに検証したものです。
| 地域・店名 | 噂の内容 | 検証結果 |
|---|---|---|
| 青森・マ〇カイラーメン | お客が保健所にスープを提出し、唾液成分が検出された | 保健所・新聞いずれの公表記録もなく、信憑性は確認できず |
| 和歌山・井〇商店 | 飲み残しスープ再利用で3日間の営業停止処分を受けた | 保健所の処分履歴も報道も存在せず、デマである可能性大 |
| 熊本・玉名の某店 | 食べログのレビューに「昔は使い回ししていた」との記述 | 食べログ以外の情報源はなく、保健所記録にも該当データなし |
ケース①:青森・マ〇カイラーメン伝説
「お客がスープを持ち帰り検査に回したら唾液成分が…」という話は、ネット掲示板から火が付いたもの。実際に保健所がそのような検査を行った事実は確認できず、投稿者自身の実名や店側の反論も見当たらないことから、都市伝説の域を出ません。
ケース②:和歌山・井〇商店営業停止メール
「3日間の営業停止」のメールが拡散されたものの、和歌山市保健所や地元紙のアーカイブには該当処分の記録が一切存在せず。逆に、風評被害を受けた同店が公式サイトで「当該事実なし」を明言しており、完全なデマと断定できます。
ケース③:熊本・玉名の某店レビュー
一部の食べログレビュアーが「昔は使い回ししていた」と書き込んだもの。しかし、投稿から数か月後にレビュアー自身が「事実確認せずに書き込んでしまった」とコメントを削除しており、根拠のない噂であったことが判明しています。
6. 本当に安心して食べるために
6.1 店主への直接確認(やれるもんなら)
-
お店に足を運んだ際、「スープはどのように管理されていますか?」と素直に質問してみましょう。店主から調理の流れや衛生管理について説明を受けることで、信頼感がぐっと増します。
⇒おすすめしませんけどね!!!!こんなん聞かれた方は不快だわ!!!!
6.2 公的情報のチェック
-
地方自治体の保健所ウェブサイトでは、飲食店の営業許可状況や処分履歴が公開されています。気になるお店があれば、「(市名) 保健所 飲食店 処分」で検索してみましょう。
6.3 情報リテラシーの習得
-
出所不明の情報は必ず二次ソースより上のところ(一次情報)で裏取りを。
-
SNSで見かけた“友達から聞いた話”は、公式発表やニュース記事で確認するクセをつけましょう。
⇒これ、ほんとに現代こわいのでどうかひとつ。
7. まとめ
ラーメン屋のスープ&ファミレスのパセリ使い回し疑惑は、多くが裏取りのない噂や誤解が原因でした。
食品衛生法や業界の調理フローを知ることで、デマに惑わされずに安心して一杯を味わえます。
今後は、
-
疑わしい情報を見つけても、すぐに流さずに、
-
複数の信頼できる情報源で確認し、
-
店主に直接質問する(空気読んで、聞かないに越したことはない)
というステップを踏んでみてください。
そうすれば、デマに踊らされることなく、美味しいラーメンを心から楽しめるはずです。
【博多豚骨ラーメン】
https://amzn.to/3SgYwCa
|
|
|
|




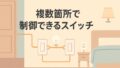

コメント