❓はじめに:「因果がないなら、関係ない…って思ってませんか?」
「チョコレートの消費量が多い国ほど、ノーベル賞の受賞者も多い」
この話を聞いたとき、多くの人がこう思うはずです。
「え? そんなわけあるかい」
「それ、偶然でしょ?」
「なんかトリックでもあるの?」
……ですが、実際にその2つのデータを並べてみると、驚くほどぴったりと一致しているのです。
これはまさに、「因果関係はないけれど、相関関係はある」という現象。
そしてこのような現象は、私たちの身の回りに意外と多く存在しています。
📊 相関関係と因果関係はどう違うのか?
● 相関関係(Correlation)
→ 2つの事象が同時に変動する関係。ただし、一方が他方を引き起こしているとは限らない。
● 因果関係(Causation)
→ Aが原因でBという結果が生まれる、という直接的な因果のつながり。
たとえば、「雨が降ると傘をさす」これは明確な因果関係です。
しかし「アイスの売上と溺死事故の件数が比例する」というのは、どちらも“夏”という第三の要因(季節)に影響されているだけです。
それでも、数字としては不思議なほど“一致”して見えてしまう。
この「偶然にしては一致しすぎた相関」が、統計の落とし穴であり、面白さでもあるのです。
🧠 思わず誰かに話したくなる!因果はないけど相関がある雑学10選
① チョコ消費量 × ノーベル賞受賞者数
スイス、フィンランド、日本…。
世界的に見てもチョコの消費量が多い国ほど、ノーベル賞の受賞者数が多いという驚きのデータがあります。
2012年に米国の医師フランツ・メッセリ氏が発表した論文では、人口1千万人あたりのノーベル賞受賞数とチョコ消費量の間に0.79という強い相関が認められました。
ただし、これにはもちろん因果関係はないと考えるのが妥当です。
チョコに含まれるフラバノールが脳に良い影響を与える可能性はあるにせよ、
「チョコを食べればノーベル賞が取れる」と結論づけるにはあまりに強引。
経済力、教育水準、科学投資など、他の要因が背景にある可能性が高いのです。
② アイスクリームの売上 × 溺死事故の件数
これは統計の教科書にもよく登場する有名な例です。
夏になるとアイスの売上も溺死事故の件数も増加します。
この2つには直接的な関係性(因果)はないものの、「暑さ=共通因子」によって比例関係が生まれているのです。
このように、“第三の変数”が存在する相関を見抜けるかどうかが、統計リテラシーの鍵になります。
③ チーズ消費量 × シーツによる窒息死(アメリカ)
アメリカでのとある統計では、チーズ消費量の増減と、寝具による窒息死の数がきれいに重なっていたというデータがあります。
もちろん、偶然以外のなにものでもありません。
この事例は「spurious correlation(擬似相関)」の代表格であり、数字が一致するだけでは何の意味もないという教訓になります。
④ ラジオの普及台数 × 精神疾患の入院数
20世紀初頭、アメリカでラジオの台数が急増した時期と、精神病院への入院者数が増加した時期が一致していました。
一見すると「ラジオが人を狂わせた?」なんて思ってしまいそうですが、実際は単なる時代的トレンドの一致です。
このように、社会の進展や人口の変化による同時進行の増減が、相関として現れることがあります。
⑤ 教育費 × 電気代(OECD諸国)
OECD加盟国の統計では、教育費と電気代がともに上昇傾向にあることが見て取れます。
一見無関係なこれらのデータですが、どちらもインフレや経済成長という背景要因に影響されているため、一定の相関を示すのです。
⑥ 海面上昇 × インターネット利用者数
こちらもトレンドベースの相関。
地球温暖化が進行して海面が上昇し続ける一方で、世界中のインターネット利用者も爆発的に増加しています。
この2つのデータを並べると、確かにきれいな相関が現れますが、直接的な因果関係はまったくありません。
⑦ コウノトリの目撃数 × 出生率(ドイツ)
ヨーロッパでは「赤ちゃんはコウノトリが運んでくる」という迷信があります。
実際、ドイツの一部地域では、コウノトリの目撃数と出生率に相関が見られるというデータが報告されたこともあります。
しかしこれは、単に田舎に行けばコウノトリも多く、大家族も多いというだけの話。
ユーモアに満ちた擬似相関の代表例です。
⑧ 爪の長さ × 忘れ物の回数
これは科学的根拠のない都市伝説的なネタですが、SNSなどで「爪が長い人ほど忘れ物が多い」なんて話がバズることがあります。
こうした“印象だけの相関”は、現実にはデータとして裏付けがないことがほとんど。
にもかかわらず、人はこうした“もっともらしい話”に納得してしまうのです。これもまた、人間の心理の相関的傾向じゃな。
⑨ Simpsonのパラドックス
「個別のグループでは女性の方が合格率が高いのに、全体では男性の方が合格率が高くなる」という統計的逆転現象。
これはサンプルサイズの偏りやグループ間の母数の差によって起こります。
この事例は、相関の見方を誤ると意思決定を間違えることを端的に示しており、ビジネス現場でも重要な統計的教訓とされています。
⑩ Anscombe’s Quartet(アンスコムの四重奏)
これは4つのデータセットが、平均・相関係数・分散・回帰直線すべて同じでありながら、グラフにすると全く異なる形をしているという例です。
この事例は、「数字だけで判断してはならない」「データは必ず可視化せよ」という統計学の鉄則を教えてくれます。
📌 なぜ「相関に騙される」のか?人間の思考のクセ
人は偶然の一致を見ると、ついそこに意味を見出そうとする本能的なクセがあります。
これを心理学では「アポフェニア(apophenia)」と呼びます。
これは人間の進化の中で、危険や機会を見逃さないように脳が“でっちあげでもストーリーを作る”癖を身につけてきたとも言われています。
✅ まとめ:相関はヒント、因果は検証が必要
-
数字が一致していても、それが原因と結果であるとは限らない。
-
相関とは「問いのヒント」であって、「答えそのもの」ではない。
-
鵜呑みにせず、背景にある第三の変数・時代・バイアスを見抜く目が必要。
ほかの雑学
🥢【知られざる“揚げ”の起源】偶然の肉脂が日本の天ぷら&唐揚げ文化を変えた!?🧐
「なぜ?」が「なるほど!」に変わる!日常に潜む言葉と習慣の超意外なルーツ10選
【検証】本当に根拠ある?昔から語られる“迷信”20選|信じてたら要注意!
ついでに
実は私たちは、数字だけでなく印象や記憶にも“相関”を見出そうとするクセを持っています。
特に、「たまたまの一致」に意味を求めてしまうと、根拠のない“でっちあげの因果”が生まれることも……。
以下に紹介するのは、そんな“それっぽいけど本当は根拠がない”因果の思い込み例です。
🌀 でっちあげの例一覧(誤った因果関係)
-
黒猫が前を横切ると不吉
→ 迷信にすぎないが、「不吉な出来事があった日=黒猫を見た記憶だけが残る」ことで因果がねつ造される。 -
満月の夜は出産が多い/事件が起こる
→ 医学的なデータでは有意差がなく、「印象に残りやすい」夜だから誤認されやすい。 -
梅干しを食べると長生きする
→ 実際に長寿な人が梅干し好きだった、という話から“でっちあげ因果”が成立している。 -
努力すれば必ず報われる
→ 努力して成功した人はいるが、「成功=努力の結果」と単純化しがち。裏には運・環境・偶然の要素が多い。 -
A型の人は几帳面
→ 血液型性格診断は科学的根拠が乏しいが、「A型=几帳面だと聞いた → そう見えてくる」という認知バイアスで強化される。 -
ゲームばかりやるとバカになる
→ ゲームをしている子が成績悪いケースを一部見て、「ゲーム=学力低下」と短絡的に結びつける。 -
勉強ができる子はメガネをかけている
→ メガネ率が高いだけで、視力と知力に直接の因果はない。イメージの相関から生まれる誤解。 -
長財布を使うとお金が貯まる
→ 金運アップ財布が流行したが、因果が証明されたわけではない。成功者の使っていたアイテムからの連想にすぎない。 -
「水をたくさん飲むと健康になる」→ 水を飲みすぎて逆に危険になる例も
→ 健康=水という単純な因果が、ケースバイケースの判断を曇らせる。
|
|
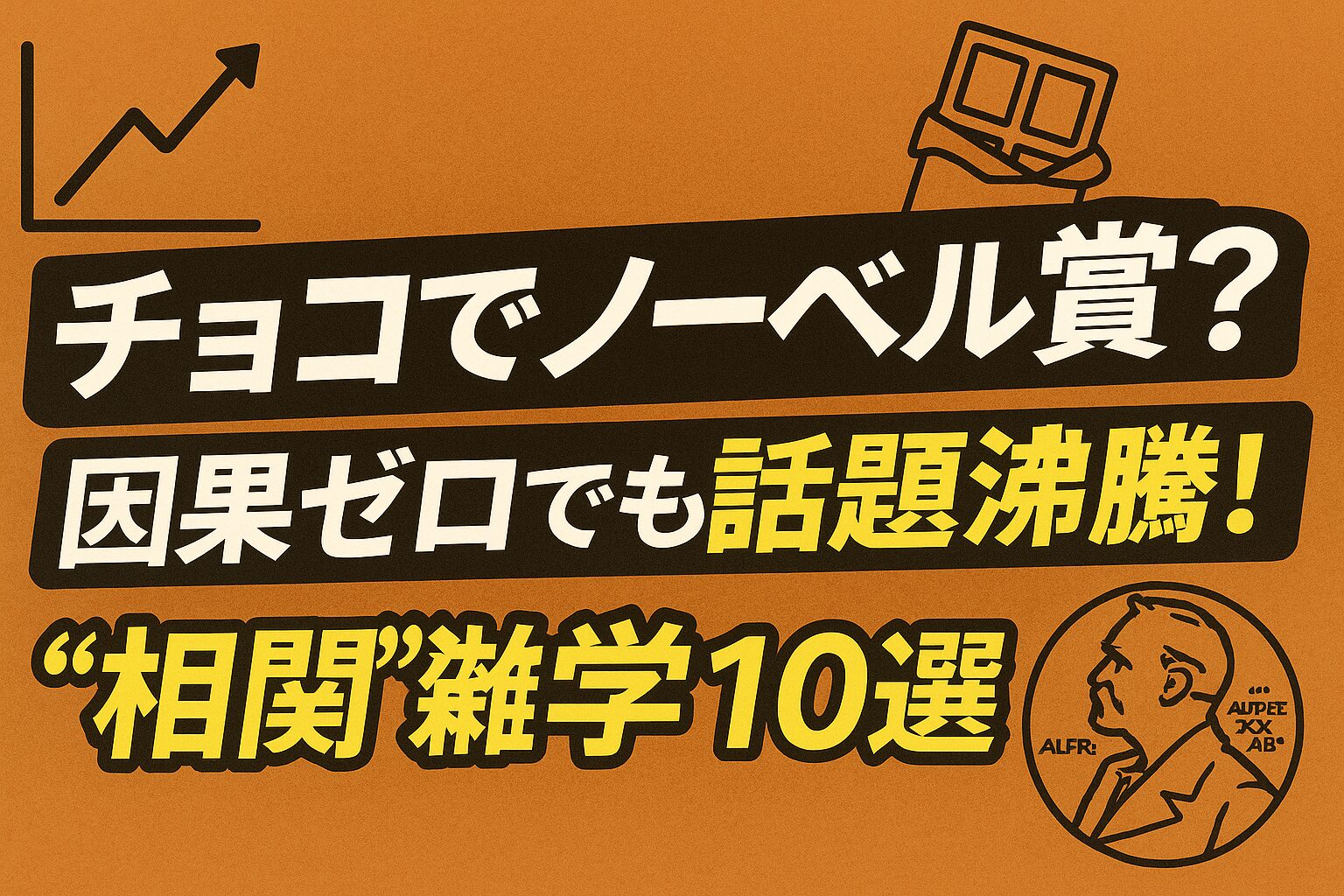


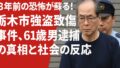
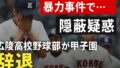
コメント