「今日のママ、また泣いてた」
夕飯を囲む食卓で、小学四年生のリオはふとつぶやいた。
朝は元気だったのに、夕方には涙ぐみ、時には怒り出す。そんな母親の姿を、彼は幼いながらに感じ取り始めていた。
父は仕事で遅く、祖母は遠方に住んでいる。母子の時間が長い家庭において、母の感情の波はそのまま家の空気になっていた。
「ママって、病気なの?」
そんな問いをきっかけに、家族にひとつの変化が訪れた——。
双極性障害と母親の役割
双極性障害(躁うつ病)は、気分の高揚(躁状態)と落ち込み(うつ状態)を繰り返す精神疾患です。この障害を持つ母親にとって、子育てという重責は時に非常に過酷なものとなります。
子どもにとっても、「ママの顔色をうかがう日々」「突然怒鳴られたり泣かれたりする不安」は、精神的ストレスとして積み重なっていきます。
とりわけ母親は、家庭の「感情の基盤」となることが多く、障害がそのまま家庭全体のバランスに影響を及ぼします。
子どもと母親の「すれ違い」はなぜ起こるのか?
1. 症状の理解不足
子どもは「ママがなぜ怒るのか」「なぜ寝てばかりいるのか」を理解できません。
母親もまた「子どもに迷惑をかけている」と感じてしまい、自責と羞恥心でさらにうつ状態が悪化することも。
2. 愛情の表現に偏りが出る
躁状態では過剰に活動的になり、子どもに対して過干渉になるケースも。反対にうつ状態では無気力になり、ほとんど声をかけることができなくなるという両極の姿が、子どもに混乱を与えます。
3. 子どもの「我慢」が習慣化する
「ママのことは黙っておこう」「自分が頑張らなきゃ」と、年齢にそぐわない責任感を背負う子どもも少なくありません。
共に歩むための5つのガイドライン
以下は、母親と子どもが少しずつ理解し合い、共に歩むために必要な視点を整理したものです。
| ガイドライン | 内容 | 実践のヒント |
|---|---|---|
| 1. 病名を隠さない | 子どもにも伝えることで安心感が生まれる | 年齢に合わせた説明を心がける |
| 2. 感情を「説明」する | 「今は悲しい気持ちなんだ」と言語化する | 子どもに理由を伝えることで混乱が減る |
| 3. 子どもに期待しすぎない | 役割を背負わせない | 子どもを「支え手」にしない配慮 |
| 4. 専門機関を活用する | 親子カウンセリングや支援制度を活用 | 家族以外の味方をつくる |
| 5. ひとりになれる時間を確保 | 母親も子どもも自分の空間を持つ | 定期的なショートステイも視野に |
専門家の見解:X(旧Twitter)から見るリアルな声
SNS上でも、双極性障害と親子関係について発信される声が多く見られます。
「母が躁状態になると、夜中に何度も電話してきて怖かった。でも、病気だと理解してから少し距離を置けるようになった」
— @familymentalcare
「母が突然泣き出した日。あの時の自分の戸惑いは今でも忘れられない。でも、今は私も母親。あの気持ちが少しわかるようになった」
— @30syufu_mental
これらの声は、当事者やその家族にとってのリアリティを強く物語っています。家族内だけで抱え込まず、社会と繋がることで、孤独感は大きく和らぎます。
支援制度と社会的な後ろ盾
日本では、精神障害者保健福祉手帳や障害年金、自治体による育児支援など、さまざまな制度があります。特に以下の支援は要チェックです。
-
地域包括支援センター:親子カウンセリングの紹介や地域支援の窓口
-
家族会や当事者会:同じ境遇の人とつながる場
-
NPO法人「ぷるすあるは」:子ども向けに精神疾患をわかりやすく解説した絵本の配布なども行っている
「病気を抱える母」と「成長する子」——その関係の先にあるもの
最後に一つ、伝えたいことがあります。
子どもにとって「母親の病気」は、一生のテーマになることもあります。しかし、それが「重荷」としてだけでなく、「理解」や「思いやり」へと変わる可能性もあるのです。
リオのような子どもが、「あの時ママが病気だったからこそ、自分は強くなれた」と思える未来を、私たちは信じたい。
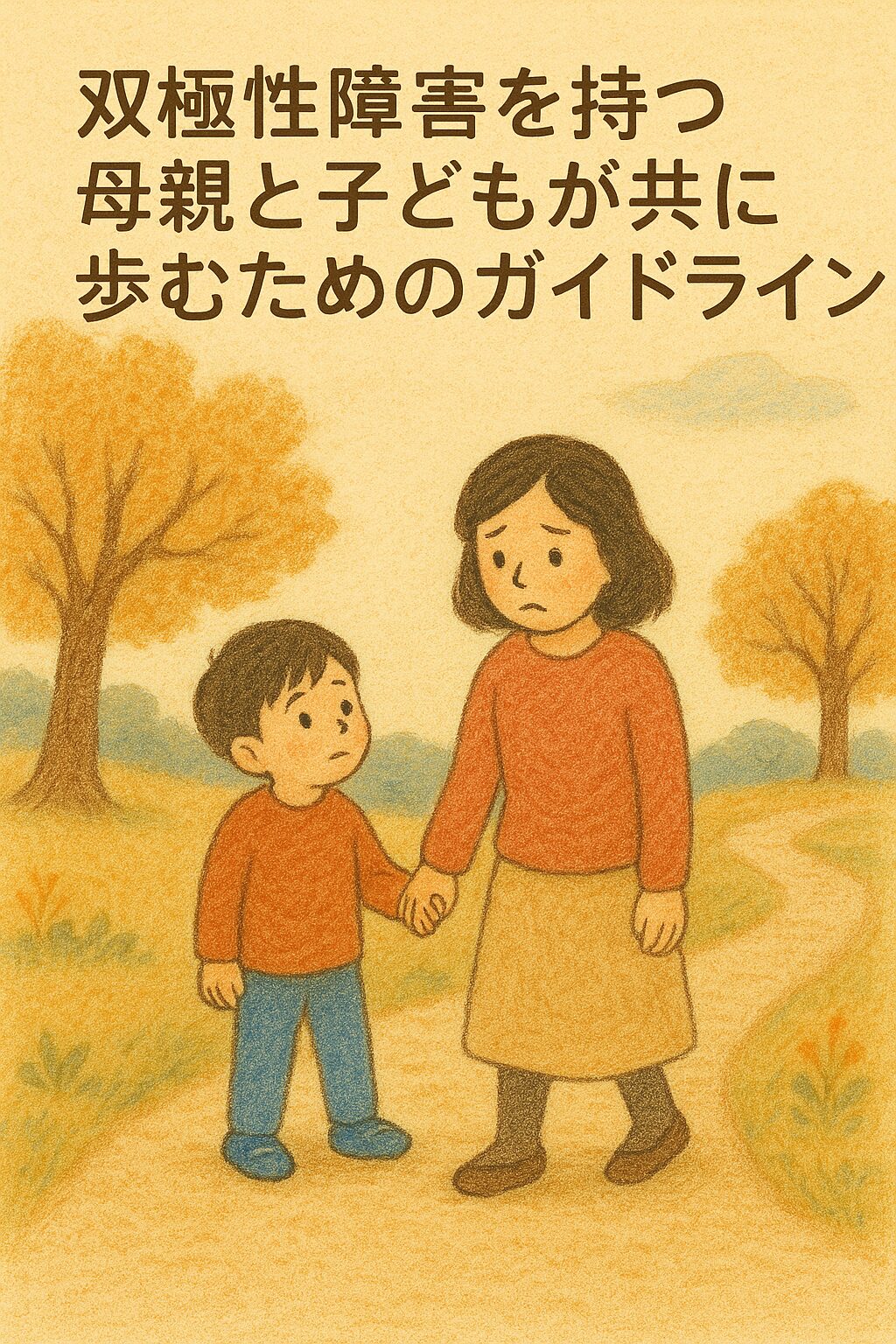


コメント