“揚げ”ってなんだ?ふと気になったんですよ
「肉を焼いたら脂がポタリ……。それをそのまま別の食材にかけてみたら、なんか美味い!もしかして、これが“揚げ物”の始まりだったんじゃ?」
──そんな素朴な疑問や、ちょっとした思いつき。実は、こういう“直感”こそが、歴史や文化の原点にあることもあります。
料理って、最初は偶然の産物だったのでは?と思いたくなりますよね。とくに「揚げ物」なんて、「焼いた肉の脂で次の肉を焼いてみたらカリッとした」とかありそうじゃないですか。
※↑私はこう推理したんですよ↑
ですが実際のところ、「揚げ」という調理法は、思ったよりも戦略的かつ文化的に発達してきたものなのです。
今回はそんな“揚げ物の起源”にまつわる、ちょっと意外でおいしい歴史を深掘りしてみましょう。
🍤「揚げる」ってどこから来たの?語源のひみつ
「揚げる」という言葉のルーツは、動詞「上げる(あげる)」から来ています。
つまり、「油の中で加熱された食材をすくい上げる」という動作から名付けられたんですね。油の中でプカっと浮いて、音を立てながら揚がっていくあの様子──まさに「浮き上がる=揚げる」というわけです。
この発想は、単に「焼く」や「煮る」といった加熱とは異なり、浮かせながら加熱する=立体的な調理法とも言えます。熱伝導効率も高く、食材の水分が一気に蒸発することで、あのサクサク食感が生まれます。
ちなみにこの言葉、江戸時代以降に一般的になったとされており、それ以前は「揚げる」という言葉は一部の料理人や貴族階級の言葉だったとか。
🥬なぜ植物性油が先に普及した?
揚げ物に欠かせないのが「油」。
そして、油にも動物性と植物性があるわけですが──
✅動物性油(ラードや牛脂)
-
狩猟文化や牧畜文化を持つ地域(欧州・中東など)で広く使われていた。
-
保存性が高く、寒冷地ではカロリー源として重宝された。
✅植物性油(ゴマ油・菜種油など)
-
古代中国では紀元前からゴマ油が使われていた記録あり。
-
仏教の普及とともに、肉食が避けられたため、植物性油が料理の中心に。
-
圧搾技術(油をしぼる技術)が早期に発達し、安定供給が可能になった。
特に日本では、仏教の戒律によって肉食が長らく制限されていたため、動物性油よりも植物性油が料理に適していたのです。
奈良時代の文献には、すでに「ゴマ油で揚げた野菜料理」が登場していたという説もあり、これは精進料理の一環としても考えられます。
🥩それでも“肉脂を使った揚げ”はなかったのか?
ここで冒頭の仮説に戻ってみましょう。
「肉を焼いたら脂が出た。次の肉をその脂で焼いたらうまかった」
この発想は、まったくもって自然で、“人類の発見あるある”とも言えるでしょう。
ただし、ここで言う「焼く」はあくまで“フライパン”に近い調理であって、食材全体を油に沈める“揚げ”とは少し異なります。
つまり、「偶然の脂→新しい調理法」という発想の芽は確かにあったかもしれませんが、
そこから「油を鍋いっぱいに溜めて揚げる」という発想へのジャンプは、文化や技術の後押しが必要だったということです。
🇨🇳揚げ文化の本場・中国では?
中国ではすでに紀元前から、ゴマ油や大豆油による揚げ物料理が存在していたとされています。
代表的なのは「油条(ヨウティアオ)」や「炸醤(ザージャン)」など。これらは油で揚げた料理や副菜で、日常的に食べられていました。
また、中国の料理本『斉民要術(せいみんようじゅつ)』(6世紀頃)には、菜種やゴマをしぼって油を得る方法や、その油を使った料理の記述も残っています。
つまり、揚げ物文化は中国で技術として既に確立されていたというわけです。
🇯🇵日本の揚げ物文化:仏教×貴族×ポルトガル
日本では奈良〜平安時代に、中国経由で精進料理としての「素揚げ」が伝来。
その後、江戸時代にはポルトガルの「フリッター文化」が伝わり、天ぷらの原型が登場します。
特に江戸期には、屋台文化の発展により、
「串に刺して揚げた魚介や野菜を提供する」スタイルが庶民に定着。
さらに明治以降、唐揚げやコロッケが広まる中で、家庭料理の定番として“揚げ物”が定着していくのです。
📱SNSではどう語られている?
X(旧Twitter)では、以下のような声が上がっています:
「肉の脂から揚げ物が生まれたって発想、ロマンあるよね」
「でも実際はゴマ油が先なのか~、勉強になる」
「仏教文化って料理にも影響してたんだ…」
意外にも、「偶然性を否定しすぎない」声と「文化的背景への納得感」が共存しており、
読者の多くが“へぇ〜”と思いながらも、納得している様子が見られました。
🧾まとめ表:偶然?計画?どっちが揚げの起源?
| 観点 | 偶然説 | 文化説 |
|---|---|---|
| 代表例 | 焼いた肉から出た脂 | 精進料理・天ぷら |
| 技術要素 | なし(再利用) | 油の抽出・温度管理・調理技法 |
| 拡張性 | 再現性が乏しい | 飲食文化として定着可能 |
| 支持層 | 一般人の想像 | 歴史学・料理研究家 |
🔚結論:ロマンと文化、どちらも“揚げ物”のスパイス
料理の起源には、偶然から始まる“ひらめき”もあれば、
文化や技術によって育まれた“知の積み重ね”もあります。
「揚げ」という調理法も、そのどちらか一方ではなく、
おそらくは「日々の生活の中で発見された偶然」が、
中国・日本の文化とともに体系化されていった、
そんな“美味しい進化の物語”なのかもしれません。


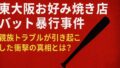
コメント